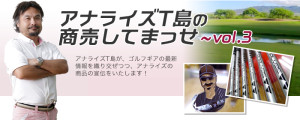昨日はテレビ番組の取材でした。三島エリアのゴルフ場での撮影で、いまどきのドライバーの試打をやってきました。天気に恵まれ撮影も順調に進み、夜は新宿で大竹しのぶさんの舞台を観ることができました。
上手い役者さんの演技はゴルフスイングにも相通じるものがあり、芝居を楽しむことに加え、身体感覚、身体表現の重要性を学べます。芝居の演技もゴルフスイングも上手い人ほど「自然」に見えますが、自然に振る舞うことと「自然に見える」とはまったく違います。不自然な動作の稽古(練習)を何度も何度も繰り返し、その結果、無駄な動きがそぎ落とされることで、演技(スイング)というのものは「自然に見える」ようになってくるのです。素人が「自然」を意識したり、頭の中でイメージして「自然な振る舞い」をやろうとしても、「自然」には見えません。そんなことをすると、大抵は「不自然」に見えてしまいます。
さて、今日のエントリーもグリップ重量についてです。
ドライバーのヘッド重量は昔も今も、190〜205gぐらいですが(男性用の場合)、グリップ重量はかなり変化しています。40年前は50g±5gぐらいでしたが、最近は‥‥軽いモノが出回っています。クラブメーカーがドライバーに装着するグリップ重量は‥‥
27~52g
ぐらいです。軽いグリップと重いグリップとでは約2倍の差があります。クラブヘッドの重さはほとんど変わっていませんが、その反対側に装着されるグリップの重さは、クラブによってかなり違ってきているのです。
では、軽いグリップと重いグリップとでどちらがいいのか?
どちらがゴルファーにメリットがあるのか?
グリップを軽くするメリットは‥‥
クラブ重量(総重量)を軽く
軽いヘッドでもバランスを出せる
この2つです。例えば280gのドライバーがあったとしましょう。ヘッドもシャフトもほぼ限界まで軽くしている場合、グリップを10g軽くすればクラブ重量を270gにできます。そして、グリップを軽くした場合、スイングウエート(スイングバランス)が重くなります。結果、クラブは軽くなってもワッグルしたり、スイングしたりするとヘッドの重みを感じ取りやすくなります。言い換えると、グリップを軽くすると「クラブ(ヘッド)を重く」することが可能になるのです。
では、これはゴルファーにとって本当にメリットがあるのか?
クラブ重量(総重量)をとにかく軽くしたい人、そして軽いクラブでもヘッドの重みを感じ取りたい人にはメリットがあるでしょう。しかし、そうでない人はメリットよりもデメリットが大きくなる可能性があります。
ヘッドに対してグリップ側が軽くなりすぎると、手元側の重さを感じ取りづらくなります。その結果、スイング中の手の軌道が不安定になるリスクが高まり、ミート率が悪くなる場合が少なからずあります。特に、ダウンスイングで手元が浮き上がりやすい人や、チーピン(引っかけ)が出やすい人には、軽すぎるグリップはメリットよりもデメリットが大きくなります。グリップが軽すぎると、ヘッドの重さに手元側が負けてしまい、ダウンスイングで手元が浮きやすくなりますし、手元が浮いてダウンスイング後半でシャフトが寝る度合いが増してくるからです。
対して、重いグリップのメリットは
重いヘッドを装着してもバランスが出過ぎない
スイング中、手元の軌道を安定させやすい
この2つです。グリップが重くなるとクラブ重量(総重量)を軽くできませんが、それ以外ではほとんどデメリットはありません。重いグリップを装着するとクラブは重くなりますが、カウンターバランス効果が得られます。重いヘッドを装着してもバランスが出づらいですし、振った時にヘッドを軽く感じます。その結果、重いヘッドが振りやすくなるのでボール初速を上げられるメリットがあります。加えて、ダウンスイングで手元が浮きづらくなるので、ミート率が良くなってきますし、チーピン(引っかけ)のミスも減らせるのです。アナライズでは5年以上前からシャフトスタビライザーという手元側を重くする器具を販売していますが、これを装着するとミート率が上がり、チーピンのミスも減らせます。総重量が20〜40g増えてきますが、それでもヘッドスピードはほとんど変わりません。
軽いグリップ、軽くない(重い)グリップ。それぞれにメリット(デメリット)はあります。だから、ダンロップのゼクシオは最新モデルに28gの超軽量グリップを装着し、ヨネックスとミズノは最新モデルのドライバーに重いグリップ(グリップエンド部分を重くした)をグリップを装着しているのです。
たかがグリップ、されどグリップ。
マーク金井は軽いグリップよりも重めのグリップ(50〜60g)を好んで使います。理由は2つあって、ひとつは200gを少し越える重ヘッドを使いたいから。もうひとつはグリップは軽過ぎない方が(重めの方が)、ダウンスイングの軌道が安定し、ミート率がアップするからです。ゴルファーによって適正グリップ重量は異なります。クラブを買い換えた時に、「なんか上手く打てない」「芯に当たりづらい」「気持ち良くスイングできない」と感じるならば、グリップ重量をチェックしてみることもお勧めしたいです〜。
(▼▼)b
マーク金井セレクションクラブコーナー出来ました
こちらも毎日更新しております。アナライズのストアブログ(T島ブログ)